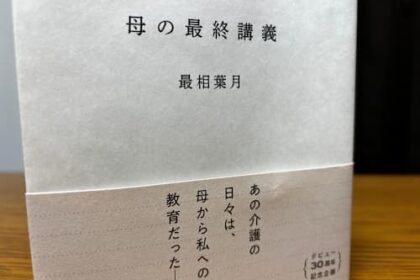常見藤代*詳しい生い立ち
わたくし常見藤代の詳しい生い立ちです。
幼少~大学時代

左が私。7才の時の写真。右は近所の仲良しえみこちゃん。
(左。才の時の写真。右は近所の仲良しえみこちゃん)
・幼稚園に入園当初、知らない子ばかりの環境に馴染めず、毎日泣いて帰ってくる。
・小学校~高校時代、教師である両親の影響もあり、勉強熱心な優等生だった。しかし友人はほとんどおらず、部活も途中で挫折。高校時代まで学校と家の往復だけの毎日を送る。
大学入学
・上智大学法学部に入学。
・入学当初は、それまでの勉強一筋人生の反動で、様々なバイトにあけくれる。
・バイト先で知り合った友人に誘われ、初めての海外旅行へ。行き先はアメリカ西海岸。その後、同じ友人とニュージーランドのツアーに参加。以後旅行にはまっていく。
・大学3年、バイトと遊び三昧の生活にも飽き、高校までの勉強一筋だった生き方に疑問を持ちはじめ、自分を変えたいと思うようになる。
・「それには環境をがらりと変えるしかない。」と長期で海外に行くことを思い立つ。大学を休学。インドネシアを半年間放浪する。
・行き先にインドネシアを選んだのは、大学での「東南アジア学」の授業の担当教授がインドネシア専門だったため。
・「父親も教授で、毎日好きな本を読んで楽しそうだったから自分も教授になった」と語るおおらかさが、当時の自分に魅力的に見えた。「その人が好きなインドネシアなら、きっといい場所だろう」と単純に考えたため。
・インドネシア行きを思い切って両親に相談したところ、父親が「お前も成長したな」と言ったのは、今でもよく覚えている。
初めての一人旅
・ジャワ島、スマトラ島、バリ島、ロンボク島などを点々とする。旅程を決めず、名もない町や村を回る。出逢うのは、観光客ずれしていない素朴な人たちだった。

泊めていただいた家の家族たちと。
・バスで隣の人が、見慣れない日本人と見て気さくに話しかけてくる。インドネシア語を二言、三言返すと大喜びし、「うちに来ないか」と誘われ、のこのこついていく。
・色々な人の家に泊めてもらう。そんなことができる自分に驚き、「眠っていた自分」のようなものを発見した思い。
・旅先で写真を撮り始める。コンパクトカメラだったが、旅で出会った風景や人を撮っているうちに、写真の楽しさを知る。
会社員時代
・インドネシア滞在中、写真の面白さに目覚め、写真と文章で世界各地のことを伝える仕事がしたいと思うようになる。
・マスコミ就職を希望したが、マイペースな性格が災いし、就職戦線に乗り遅れる。実力不足で入社試験にことごとく落ち、結局損害保険会社に就職する。
・好きな写真や文章の道をあきらめられず、仕事帰りにライタースクールに通う。そこのクラスメートに「常見は写真の方が合っている」と言われ、写真学校にも通うように。25歳にして初めて一眼レフカメラを手にする。
・日比谷公園での野外実習で受講生たちが花や噴水などを撮る中、公園のベンチで寝ているホームレスの足の裏を撮る。当時から風景や物より人に興味があったようだ。
退職して海外へ
・会社の休みを利用してはヤップ島、ベトナムなどへの旅行。もっと世界のあちこちを見てみたい、広い世界を知りたいと強く思うようになる。
・一方でフォトジャーナリストの仕事に興味を持ちはじめる。写真の授業でユージンスミスや長倉洋海氏の写真に影響を受ける。
・写真展に足繁く通い始める。写真展で知り合った写真家の縁で、フォトジャーナリストの集団に出入りするように。
・メンバーのフォトジャーナリストたちは自分のこだわりのテーマや得意なフィールドを持って取材しており、自分もそのような「何か」を見つける必要を感じる。
・「写真のテーマを探したい」、「同時に広い世界を見たい」という2つの思いが重なり、長期で海外に行きたいと思うようになる。
・しかし会社を辞める勇気はなく、会社を辞めるかどうしようか?と考えて悶々として過ごす。
・その頃、銀座の写真ギャラリーで一人のカメラマンに会う。ラーメン屋で一緒にラーメンをすすりながら「写真が好きで写真の仕事をしたいと思っているんです」と打ち明ける。
すぐさま「会社やめれば良い」、「人生には嫌いなことをしている時間はない」と言われ、人生はシンプルに考えていいんだと目からウロコが落ちた。
・写真のテーマを探すため、世界一周へ出発。予定では東南アジアのタイをスタート地点に陸路で西へ。アフリカ、北米、南米などをぐるりと回り、1~2年で帰国するつもりだった。
・タイからミャンマー、バングラデシュ、インド、パキスタンと旅をするうちに、イスラムの国々を多く訪れ、現地の人々の温かさに触れる。
バングラデシュでは、飛行機で一緒だった男性が、現地が初めてのる私を心配し、ホテルまで案内してくれた上に、ホテル代を支払ってくれた。
イランでは何人ものイラン人に家に呼ばれる。シリア、ヨルダン、エジプトで同様の経験をする。
それまで「イスラム圏の国々は危険な場所」「イスラムは怖い」というイメージを持っていたが、そのイメージが覆され、自分が見た現実を伝えたいと思うようになる。
イスラムをテーマに
・日本を出て10か月後、エジプトに到着。それまでに安宿で出会うバックパッカーから、「エジプト人はインド人以上にボる」とたびたび聞かされていたため、身構えて入国。
・エジプトにたどりつくまでの旅で、「イスラム圏をテーマにしたい」という気持ちが固まっていった。
・エジプトに到着したのはラマダン中。断食明けの時刻に外を歩いていると、道端のトラックの荷台でラマダン明けの食事をしている男性に誘われ、ごちそうになった。
・着いた当日、町中を歩いていて、ふいに「ここに住みたい」と思う。この町が自分にしっくりくるのを感じ、カイロに暮らすことを決める。
・カオス極まりない町だった。 ベンツの隣をロバ車が走り、近代的なビル群のすぐ隣に、時間が止まったような中世の街があった。
役所の窓口でサンドイッチを食べている人がおり、アパートの上階の人が下にゴミを投げる。
・一方、老人が道を横切ろうとしていると、どこからともなく若者が現れて手を引く。車いすの人が電車を降りようとすると、周囲からさっと人が集まり、手助けする。社会の秩序には欠けるが、それを補う人としての温かさや絆があると感じた。

シリアの村の村長さんのお宅にて。
・「言葉を話せれば人の暮らしに入っていきやすい」とのインドネシア旅行の経験から、言葉を学ぶため、語学学校に入学。
・しかしアラビア語のむずかしさに早々と挫折。その後は知り合った人の家に呼ばれたり結婚式に参加したりし、写真撮影をしながら過ごす。
エジプトから帰国
・帰国後は、エジプトを中心としたイスラム圏をテーマにしたいと思っていたが、当時師事していたフォトジャーナリストに「中東をやるならパレスチナに行かなければ」と言われ、パレスチナに向かう。
・イスラエル軍に家を壊され、土地を追われるパレスチナ人のルポが、「サンデー毎日」(毎日新聞社)のトップグラビアを飾る。
・しかし「これは本当に自分のやりたいことなのか」という気持ちもあった。「事件」よりも「普通の人の暮らし」に興味があった。
・師匠に「普通の人の暮らしを紹介する媒体はない」と言われるが、根性なしのためパレスチナから足が遠のいていった。
かといって、確固たるテーマやフィールドもなく、エジプトやリビア、シリアなど中東諸国へ足を伸ばしては気になるものを撮影し、発表を続ける。
主な発表媒体は「AERA」「週刊朝日」「中央公論」「婦人公論」「週刊新潮」「NHKアラビア語講座」「国際協力」「世界」「潮」など。
・同時にライター業に従事。「pink」(マガジンハウス)でピンク記事を書き、また「あなたにエール」(ベネッセ)などで記事執筆、写真撮影を行う。
・2000年頃から住宅雑誌でも記事を書く。「ニューハウス」、「MEMO男の部屋」「美しい部屋」などで、建築家が設計した家を取材。光や風をふんだんに取り入れる工夫をこらした住宅に取材の面白みを感じた。
・ライター業はそれなりに順調だったが、心のすみに「本当に自分のやりたいことだろうか」という思いがあった。
「写真のテーマを探すために海外を放浪し、イスラム圏というテーマを見つけ、エジプトに住んだのにもかかわらず、今全くかけはなれた事をしている。」
・そこでエジプトの写真展をしようと思い立つ。エジプトの路上で出会った何気ない温かい表情やしぐさなどのスナップ写真を集めた「Welcome to Cairo!」(1999年・新宿コニカプラザ)。自分にとって初めての写真展だった。
砂漠のノマドとの出会い(2003年~)
・なんとなく中東に通いつつ、何か確固たるテーマが欲しいと思っていた時、ふと以前から遊牧民に興味を持っていたことを思い出す。
元々シンプルでモノを持たない暮らしが好きで、大学時代からテレビ、洗濯機(一時は冷蔵庫も)なしの生活をしてきた。
「パパラギ」、「海からの贈り物」、「森の生活」など、元祖シンプルライフ的な本が愛読書だった。
究極なシンプルライフが遊牧民の暮らしだと勝手に思い、エジプトの遊牧民について調べ始める。
ナイル川東の砂漠に暮らす「ホシュマン族」という遊牧民についての本を見つけ、著者のウェブサイトからメールを送る。一時間後に返事が来て、族長の連絡先を教えていただく。

エジプトの砂漠に一人で暮らす遊牧民女性サイーダ(左)と。右はサイーダの息子の奥さん。
・族長に紹介されたのが、ラクダをつれて女性一人で移動しながら暮らす女性サイーダだった。
夫や子どもたちは、定住地で観光客相手の仕事をしているが、彼女は自然とともに暮らす砂漠での生活が捨てられず、一人きりで従来の生き方を守っていた。
「こんどはオトコをつれてこい」「息子はオッパイ吸ってるときは母親のことを覚えてるけど、成長したらオッパイを忘れてタバコを吸う」などと言う、茶目っ気たっぷりな人柄に、たちまちひきこまれた。
・サイーダの取材を初めて2年目に、エジプトでレーシックの手術を受ける。砂漠で満天の星空の下で眠るうちに、裸眼で星空を眺めたくなったのが理由。
・2008年の取材中、原因不明の微熱が続き、その後足がしびれて歩くことができなくなる。やっとのことで帰国。実家の近くにある病院を受診したところ、精密検査が必要と言われ、大学病院で1ヶ月ほど検査入院。
「将来歩けなくなる可能性もある」と医師に告げられ、「もうカメラを持って砂漠にいくことはできないかもしれない」と絶望的な気持ちになる。幸い点滴治療で症状は回復した。
・以来、健康に人一倍関心を持つようになり、無農薬玄米や有機野菜をとりよせるようになる。
・2006年、サイーダの写真展「Becoming the Legend」(2006年新宿コニカプラザ)を開催。
「私たちの知らない豊かさを思い出す」「足を知ることの大切さを知りました」など好意的な評価をいただく。
・「砂漠のサイーダさん」(2009年)を出版。それを機に「旅の文化研究奨励賞」受賞(2012年)を受賞。
・開高健ノンフィクション賞にノミネートされる。受賞は逃したが、2012年12月に「女ノマド・一人砂漠に生きる」(集英社新書)を出版。